| メーカー | スクウェア | 発売日 | 1999-02-11 |
| 機種 | PS | ジャンル | RPG |
| 評価 | ★★☆☆☆ |
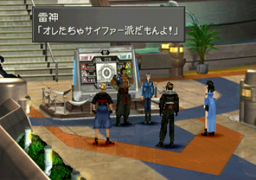
|
FFシリーズ最大のヒット作。前作で先鋭化された、いわゆる中二病要素はいよいよ強化され、正直私についていける世界ではなかった。 |
●
面白さあたりの売り上げ
ついに第8作目だ。前作が、CGを使った新しい世界観を見せつけ、地位を確立したため、この作品は大変な売り上げになった。これを書いている2009年現在において、ファイナルファンタジーシリーズ最高の売り上げである363万本を記録している。これは日本の歴代ゲームソフトにおいても11位の成績である(ちなみに12位はWiiスポーツなので、この文章を発表する頃には抜かれている可能性はある)。
と、非常に素晴らしい売り上げを誇った本作であるが、私は駄作だと感じたし、世間的な評判もあまり良くない。様々な理由があるものの、このゲームがFFシリーズ最高の売り上げという事は、これ以降の作品では売り上げを落としているわけで、それはある意味この作品が駄作だった事と多少は関係していると思われる。初代からずっとシリーズが続いてきて、途中から入り始めた「ダメな部分」が凝縮されてしまったような作品だと言える。
さて、このゲームは、前作の7で顕著だった「オタ中学生が考えたような設定」を引き継ぎ、更に進化させている。痛々しい設定を持った美男美女が痛々しい冒険をする、みたいな。
主人公スコール・レオンハートやそのライバル、サイファー・アルマシーは、バラムガーデンという学園の、傭兵集団であるSeeDの候補生である。SeeDね。真ん中のe二つが小文字。なんで学園で傭兵?と思うかも知れないけどとにかくまあそういう設定になってるとしか言いようがない。傭兵だから、時々戦争に出かけるし、学園であるから風紀委員がいるし学園祭もある。なんというか、ほんと、中学生の、しかも腐女子と呼ばれるような方々が好きそうな設定である。大体、「風紀委員」なんて現代においてはその手の漫画とかでしか見ないよね(私は「三軍神参上!!」で知ったかなあ…。古いよね)。
世の中、ライトノベル、略してラノベというジャンルがある。文学としての小説というよりも、漫画やアニメに近い形態の、簡単に言えばオタク向けの小説なのだが、このFF8のノリはそれに近い。細かい考証や、話としての重みは抜きにして、オタクが「かっこいい」とか「萌え」とか思えば勝ち、というジャンルなのだ。だから、傭兵で学園で風紀委員で、とかなっても全然構わないわけだ。そういうノリなのだ。
そのノリは、主人公たちの武器にも現れる。主人公スコールとそのライバルサイファーは、「ガンブレード」という武器を使う。一見片刃の大剣だが、鍔元に引き金と弾倉とハンマーがあり、柄は銃のようにつかむ。大剣のようだと書いたが、むしろリボルバー式の銃のバレル部が剣になっていると書いた方がイメージしやすいかも知れない。で、主人公たちはこれで時々はカキンカキンとチャンバラしつつ、時々は撃つ。撃つと刀の部分が回転しながらビューンと飛んでいく。「そんな小さな装薬で重い刀が飛ぶのか?」「飛んだとしても反動で腕折れないか?」「そんな持ち方でチャンバラできるのか?」「だいたい刀身が一回飛んでったらおしまいじゃん」などと50個くらいツッコミが思いつくだろうが、考えちゃいけない。ラノベなのだ。かっこ良ければOKなのだ。私はあまりこれをかっこいいと感じないのだが、こういうのは私に向けてデザインされているのではないのだ。
もちろん、前作と同様、そんな大剣つきの銃を片手で振り回せる膂力の持ち主なのに、ゴツゴツの戦士系のキャラではなく、みんなほっそりとして髪の毛バッチリセットしたホスト・ホステス系のキャラばかりである。このへんの設定や造形の痛々しさは、デザインを担当している野村氏の趣味が多分に反映されていると思う。
野村氏は、前作の落書きレベルのイラストからすると多少絵はうまくなったが、基本的にキャラの描き分けが出来ないので、今回は額に傷があるとか、顔に刺青をしているとか、そういうので区別しているようだ。
どうにも、小手先のテクニックばかりうまくなり、絵の本質がうまくならない人なので、私は全く評価していない。
でもって、良く分からない理由で主人公スコールは、レジスタンスの(またかよ)リノア・ハーティリー、バラムガーデンの教師キスティス・トゥリープ、同級生のゼル、セルフィ、他校の生徒であるアーヴァイン・キニアスらと、このゲームのボスである魔女を倒しに出かける事になる。
これはこの手のRPGの欠点なのだが、小イベントの積み重ねから大きなイベントにつなげていくというスタイルを取っているため、「あれ、なんで冒険してるんだっけ?」と途中で思わせるようになっている。結果的に、上記のような構成のパーティで旅をする理由があまり明白でない。
このように、このゲームは週刊少年ジャンプのテンプレ漫画と同じような欠点を抱えている。極端なキャラクタの記号化の結果、役割や性格だけがキャラに与えられ、物語や必然性がおろそかになってしまうのだ。
主人公スコールがなぜ魔女を倒さなければいけないのか、良く分からない。またヒロインのリノアとなんか恋愛関係になるらしいのだが、なぜそういう関係に至るのかも良く分からない。先生やら同級生やらもなんでついてくるのか良く分からない。ライバルのサイファーは主人公たちに立ちふさがるのだが、良く良く考えるとなぜそんな事をするのか理由が分からない。そもそも、魔女がなんでそんな悪い事をしようとするのかも、意味不明である。
要は、設定しかないのだ。この子はヒロインだから主人公と結ばれる。この人はライバルだから主人公の邪魔をする。この人はラスボスだから倒されなければいけない。という、キャラクタの関係性だけで話が進むため、「なんで?」という印象が常にプレイヤーに残る。これを製作した人に聞けば、恐らく「キャラ設定がそうだから」という事以上の話を出来ないだろう。
まあ、まさにライトノベルである。
で、いっそもうストーリーはどうでもいいからとにかく仲間と魔王を倒すんだ、という割り切ったお話にしてくれれば、それはそれで受け入れられる。しかしこのゲームでは、キャラの設定をより強めようと、お話はお話で語ろうとするため、困ってしまう。
そのストーリーというのも、前作に引き続き、意味不明系というか、相変わらずエヴァンゲリオンの影響を受けたような精神世界系のお話が混じってきてヤレヤレという感じだ。主人公スコールは夢の中でもう一つの人格としての体験をする事になる…みたいな感じなのよ。もうウンザリ。
そんな感じで、キャラの設定だけを繋げて物語にしたような(ドラマはなく、キャラに与えられた設定を説明していくだけの話)、良くある腐女子向けジャンプ漫画みたいな、最悪のシナリオである。
さて、ストーリーについても今までとはだいぶ雰囲気の違う、奇妙なものだというのは理解していただけたかと思うが、ゲームシステムに関しても、今までのFFとは一味違っている。
まず一番違うと感じるのは、「魔法」を唱えられない事だろう。魔法そのものはあるのだが、今までのシリーズとはだいぶ扱いが異なる。今回の魔法は、敵から奪って使用する事になる。この、敵から魔法を奪う事を、ドローと言う。ケアルとか、ファイアを敵から奪うのだ。1種類につき、100個まで奪う事ができる。でもって1個ずつ使って魔法を発動させる。
つまり、今回の魔法はもうアイテムだと思っていい。今までも、使うと魔法が発動するアイテム(なんきょくのかぜなど)があったが、あれを敵から盗んで使うのと全く一緒である。
まあこれだけなら、単に「なんきょくのかぜ」がたくさん盗めるFFというだけで、「どうせ使わないからいいよ」って事になる。実際、魔法の用途としてはその通りだ。しかし、今回ドローした魔法にはもう一つ使い道がある。それがジャンクションシステムだ。
今回の召喚獣は、ガーディアンフォースと呼ばれている。…いちいち呼び名変えるのなんとかならんかね。
で、このガーディアンフォースに、ドローした魔法をジャンクションできる。そのガーディアンフォースをキャラにつけると、ステータスが上がる。ステータスはHP、力、魔力…のように複数あり、それぞれの箇所に魔法をジャンクションする。すると、その魔法の個数に応じて能力が上がるわけだ。例えばHPというステータスにケアルガをジャンクションすると、所持数によってHPがいくつかプラスされる。
このせいで、上記のように「盗んで使う」タイプの魔法だが、ジャンクションを考えるとなかなか使えないというジレンマがある。
さて。
噛み砕いて説明したが、全然分からなかったと思う。正直、私も良く分からなかった。
まず、変な用語を使いすぎである。従来の召喚獣をガーディアンフォースと言い、魔法を盗む事をドローと言い、それをステータスに装着する事をジャンクションと言う。今までのシリーズで使われてきた用語ではないし、かと言って一般的に使われている用語でもない。この手の要素がこのゲームにはたくさんある。恐らく、中二病的というか、「今までみんな使ってなかったこんな用語を使うとかっこよくね?」みたいな、オタク中学生にありがちな思いつきレベルの要素がかなり多いのである。それは先述の「SeeD」だとか「ガンブレード」とかも同様である。制作者の「これかっこよくね?」が出てしまい、プレイヤーが置いてけぼりなのである。
そしてまた、用語の話だけでなく、概念的にも分からない。魔法を敵から盗み(吸い取り)、ガーディアンフォースのHPや体力にジャンクションする。システムとしては分かるが、具体的に何をしているのかさっぱり分からない部分がある。イメージが湧かないのだ。敵からドローした魔法はどんな形をしていて、どんな状態になっていて、それをガーディアンフォースにジャンクションするとは一体何なのか、またHPや力にジャンクションすると言っても、それは何か場所が違うのか、方法が違うのか、その一つ一つが良く分からない。現実に置き換えられないのだ。そしてまた悪い事に、恐らく制作者側でもそのあたりはイメージできてないらしく、グラフィック等でも曖昧にされる。
結局この二重の意味不明さが、システム全体をかなり分かりづらくしている。
システムをしっかり理解して、自分の中で咀嚼してやれば、楽しめる部分もあるとは思う。しかし、多くの人がそこまでは至らなかった。実際、私も真剣にジャンクションシステムを研究し、使いこなそうという気はなかったし、私はこのゲームは借りたのだが、元々持っていた人やその友人もみな、「適当にやってた」と述べている。
その他、一つ一つの要素は、実は良くできている部分もある。だが、そこまで行けてない人が多いのは、まず一つはそれを覆っている「表面」の部分にある。例えば「ジャンクション」だとか「ドロー」だとか、何度も書いている意味不明なカッコつけだけの用語等が、一般ユーザの理解を遠ざけている。同様に、これは私だけかも知れないが、このゲームを覆う「表面」としてのシナリオ、キャラクタ設定等も気になる。美男美女が学園でSeeDでガンブレードを持って…みたいなのが、なんかこう上っ面な空気を醸し出してしまっている。
結果として、内容的に面白い要素があったとしても、そこまで踏み込めなくなっているのだ。そういうシナリオやキャラの雰囲気が好きか嫌いかだけしか残っていないように思える。
また、ゲーム本編もそういう謎に包まれているが、サブゲームも謎い。
この世界では、カードゲームが流行っているという設定になっている。この頃色々トレーディングカードゲームなどが流行してきたので、それに合わせたのだと思う。プレイヤーが冒険していると、それぞれの街に、カードゲームにハマってる人みたいなNPCがいて、その人に対してデュエルを申し込める。
が、このゲームはあまりマジックザギャザリングのような、カードバトル式のゲームとは違う。なんとも言えない、独自のゲームだ。カードゲームと言いつつ、盤面にカードを並べて行って奪ったりするので、オセロのようなボードゲーム要素が強い。各カードには、上下左右それぞれへの攻撃力が書いてある。これを並べると、それぞれの方向に対する攻撃となり、それぞれの方向の敵カードとの数値比較をして、勝ち負けを決める。
まあこれが基本ルールで、他色々追加ルールがある。これも謎システムで、追加ルールはどこかの地方からスタートして、プレイヤーが冒険するに従ってルールが他の街にも広まっていく、みたいなイメージになっている。だからあまり変なルールが追加されそうなら、それが流行らないように色々工夫しないといけない。
正直、どこが面白いのか良く分からないゲームだった。カードの強弱も良く分からないから手札の組み方もいまいち分からないし。一応ルール上、特定の方向の数値がでかいのが攻撃型で、まんべんなく高い数値なのが防御型っぽいイメージになるのかなあ。でもなんかこう、ここが勝負どころ!みたいなのが分からないからいまいち盛り上がらない。
私の弟はこのカードゲームは「必勝法を発見した」と言っていた。それが何だったか、先日二人で話したがいまいち思い出せない。確か、「鉄巨人」という全方向に強いカードを準備し、意図的に弱いカードを置いて、相手に弱いカードで囲ませて取らせる→空いたところに鉄巨人を置いて周囲を総取りする、みたいなやり方だった記憶がある。とにかくそれを見つけてからはカードゲームで負けなかったので、弟からしても「何が面白いか分からない」という事だったようだ。
ちなみに私の弟も、途中でゲーム自体放り投げたらしい。あまりにつまらないので、「雨ざらしの刑」とか言ってベランダに長期間(何年も)、ケースごと放置していたようだ。
私はFFシリーズは3以降は大体発売日近辺に買って、クリアしていた。
が、このFF8は買わなかったし、借りはしたけどもクリアしなかった。今まで書いたような、ストーリーやキャラのうざったさとか、システムの意味分からなさが積み重なって、進めるのが辛くなってきた。
他に知り合いで投げた人がいて、聞いてみたら、「攻略本を見たら、最強アイテムの材料は最初の方のモンスターからしか盗めず、しかも取り逃すともう戻れない」みたいなのを知ってしまい、やる気なくしたそうだ。
このような取り逃すと戻れないみたいなのは前からあったが、FF7の頃からだんだん意図的になってきたように思う。
この背景としてまことしやかにささやかれているのは、攻略本を買わせるための仕組みにしているのではないか、という噂である。特にこのFF8は、「アルティマニア」という分厚い攻略本が、スクウェアの肝入りで出版された(実際には実質子会社のデジキューブの販売。その後スクウェアエニックスが事業継続)。自社の有名タイトルを、やたらデータ豊富で複雑なものとして作り、その分厚い攻略本を売る、という自作自演が可能になったわけだ。しかも、上記のように「取り逃すと大変なものがあるから攻略本買ってね〜」などという仕組みを入れる事もできる。
私は、多少この噂はうがち過ぎではないかと思うが、ただ実際FF8のアルティマニアはやたら売れたし、そういう儲け方が可能なのであれば企業だって躊躇なくやってくるだろう。だから、多少の意図はあったのではないかと思う。
(※余談だが、このアルティマニアは、あのパソコンサンデーにも出ていた山下章氏の会社が制作している)
ま、私はそれとは特に関係なく、飽きてやめたが…。
実際、ネットの評価を見てもFF8はあまり高くない。私と同じように、ストーリーだとか、システムだとかに不満を持っている人は多い。
ただそれとは別に、やりこんでいる人もいて、そういう人たちは逆に高く評価している。アビリティやガーディアンフォースをうまく使っていくと、FF8の楽しさが分かってくると。確かに、そうかも知れない。が、結局私はそこまで至らなかったので、評価は低い。
でも、ちょっとは丸くなったので、★1はやめておこう。★2くらいで。スペランカーの時に、面白さあたりの売り上げ数値(つまらないのに売れると高くなる)は、FF8には到底及ばないと書いたが、それはさすがに撤回…うーん、やっぱどうしよ。うむ、撤回無しの方向で。