| メーカー | コナミ | 発売日 | 1998-09-03 |
| 機種 | PS | ジャンル | アクション |
| 評価 | ★★☆☆☆ |
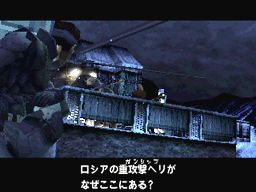
|
MSXで好評だったスニークアクションゲームの続編が、ポリゴンを活用した3Dの最新ゲームとして登場。ゲームとしての素性の良さと、全編にあふれる衒学趣味とがどうもアンバランスだった。 |
●
イタいゲームとはこの事だ
MSX2版として最後に出た、メタルギア2ソリッドスネイクの続編が、8年も経ってようやく出た。それがこのメタルギアソリッドだ。うーむ、なんかタイトルが大変紛らわしい。メタルギアなんたらというタイトルにするのはいいけど、ソリッド以外の単語にすれば良かったのに。
ゲームとしては、もちろんこの当時のゲームだから3D化されていて、3Dならではの表現やシステムもあるが、大体の画面では上から見た視点で敵兵の動きを見ながら物陰に隠れたり、戦ったりするという、2Dゲームに近い操作系になっている。という事はもちろん、MSXで出ていた前作までと、ある程度までは似通った動きが出来るという事だ。
実際、ゲームの雰囲気は似通っている。ほとんど素手に近い状態で適地に潜入し、物陰に隠れたりしながら敵を倒し、装備を奪う。もし敵や監視カメラに見つかると、発見状態になり、敵がワラワラ来るので、落ち着くまで隠れるか、諦めて敵を全滅させるかを選択しなければいけない。そんなゲーム性自体は、MSX版のものを引き継いでいる。
もっとも大きく進化したのは、ムービーや、トランシーバーを使った演出による、ストーリーの充実だろう。
もともと、MSX版から背景設定から凝っていて、ソリッドスネイクなどは説明書にフォックスハウンドの装備やら糧食やらについて書かれた謎の設定資料があったりして、良く言えば凝り症、悪く言えばオタクの衒学趣味が凄かったのだか、プレイステーションになってそれが大爆発した。
とにかく主人公、無線で語る味方、それから敵たちが語る語る…。やたら説明しまくる。身内の間では、「不凍糖ペプチド」と言う単語だけで、「小島監督のうざい衒学趣味」という意味で通じるくらいだが、そういうようなオタク系ギミックと、その説明に満ち溢れているのだ。
ゲーム全体の流れは前作までと良く似ていて、スニーキングアクションの体裁を備えているものの、要所要所でボスが出てきて、それを倒す事でひと段落という、従来のゲームの文法も備えた仕組みになっている。これ自体はいいが、ボスがまーた良くしゃべるんだよね。自分の背景とか、ギミックの説明とか。
そんなのを延々聞かされた挙句、ストーリー全体が「種の寿命」とかなんとか、うさんくさい方向に進んでいく。
正直言って、私はこういうSF的ギミック自体は好きだ。そういう映画や漫画は良く見る。
ただ、このメタルギアソリッドについてかなり否定的に書いているのは、まずそれらがかなり説明的である事、つまりゲームの流れ上必要な説明ではなく、小島監督が説明したくて仕方ないから説明していて、それを見せられるというウンザリ感を強く感じるのだ。
それともう一つ、それらのSF的ギミックとかも、なんか薄っぺらく感じる。どこかのSF小説で読んだ事があるとか、「ニュートン」とかに掲載されていたような、浅い感じなのだ。
もともと、例えばブレイドランナーであるとか、士郎正宗あたりの漫画から来てそうな、雰囲気SFみたいなネタが多かったが、それを延々見せられ続けるのは辛い。
これは私だけの感想ではなく、友人もそうだった。
私はこのゲームを弟に借りたものの(以前メタルギア2のレビューで書いた通り、弟はメタルギアが大好きだった)、ほとんど放置していた。で、その後友人が遊びに来て、暇だからという理由でうちにずっといたが、私自身はX68kのゲーム作成に忙しく、「悪い、適当に遊んでて」みたいな感じで放置していた。その時その友人が、ゲームの棚からこのメタルギアソリッドをひっぱり出してきてプレイし始め、結局クリアしたのだ。
私もそれを横目で見ながら、友人と二人で、「またボスが自分語り始めたよ…」「また説明始まった」というように笑いながらツッコミを入れていたのだが、結局クリアした友人が語ったのは、「いやー、このゲーム一人でプレイしなくて良かったよ。一人だったら寒くて死ぬところだった」という事だった。全く私も同感だ。
かなり辛辣な批判を書いているので、反発する人もいるかも知れない。得てして、この手のゲームはいわゆる「信者」を作りやすいので、そういう人が見ると腹が立つだろう。
ただまあ、このコーナーは私の個人的な感想を書くところであって、そこまで客観的ではない。私の主観で語る限り、このゲームの語りは薄っぺらく、また寒い。
とは言え、ゲーム自体は面白いし、音楽などの演出も良い。だからプレイ自体は楽しいと思う。それだけに、シナリオ説明部分の冗長さ、衒学趣味がなんとも鼻につくのだ。
あと、これはダメというわけではないが、他と違うなという意味で気になったのが、色々な部分で出てくるメタ要素だ。
これは前の作品からもあって、MSX版でもリセットボタンを押せとか、パッケージ裏の文字を読めなどという、現実世界側の情報に触れる、いわゆるメタ要素があったのだが、今回もかなりある。
私が最初にそれに違和感を持ったのが、敵ボスがナレーションで「×ボタンで何々をしろ」みたいに説明してきた時だ。普通こういうのは、天の声として画面に表示するに留まり、敵キャラにしゃべらせたりしない。これを聞いた時点で、ああメタ要素をだいぶ許容しているんだな、と感じた。他のゲームとは趣が違う。
小島監督はこれを利用して色々な遊びを提供しており、特にサイコマンティス戦などは、前述の友人と一緒に「こうするんじゃね?」みたいに言って楽しんでた記憶がある。
このように、ゲーム全体に小島色がかなり出ている。
そのせいか、クリアした後のスタッフロールには、小島監督の名前があちこちに出てくる。特に我々に大受けだったのが、「首肩ゆらし数値」という謎のロールに小島監督の名前があって、だいぶ吹いた(なんでも、今回のMGSはモーションキャプチャーを使っておらず、手付けでモーションを作っているので、会話画面でこういうデータを作る人が必要らしい)。
出たがりというか、名前出したがりなところが見て取れる。
さて、だいぶ批判的に書いたが、各種鼻につく要素があるものの、ゲーム自体の素性は良い。そのためか、続編が多数作られ、その後コナミの看板タイトルの一つになっていく。
MSXでひっそりと遊んでいた、隠れた名作的な雰囲気だったものが、3Dの時代に続編が作られて人気シリーズになった。ふつうこういう時、一抹の寂しさみたいなものを感じるが、この作品に関してだけは、「遅かったな」と感じた。もっと早くこうなって良かったのに、という感じだ。
だからこそ、ゲーム性だけはブラッシュアップしつつ、衒学趣味を少し抑えたらなあ、という残念さが気になった。