| メーカー | エニックス | 発売日 | 1995-12-09 |
| 機種 | スーファミ | ジャンル | RPG |
| 評価 | ★★★☆☆ |
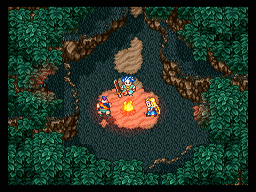
|
ドラゴンクエストシリーズ最新作が、前作から3年の時を経て登場。様々な意味でシリーズ集大成的な作りになっている。しかしその分、以後の続編に引き継がれる欠点もクローズアップされてしまった。 |
●
特技が強すぎる
前作から3年とかなり間が空いたが、95年の暮れにドラクエVIは発売された。もう時代はプレステだのサターンだのの次世代機ブームになっている頃だった。
ROMの容量に比例してきっちり値段が高くなっており、弟と折半して買った記憶がある。
で、今6の目新しい点を書こうとしてシステム面をつらつら思い出してみたが、あんまり無い事に気づいた。全体的に、今までのシステムを使いまわし、組み合わせている。3に出てきた転職システムや、5のモンスター仲間システムとかね。
一応6の新しいシステムとして、「かっこよさ」というのがある。今回は武器や防具にかっこよさ度が設定されていて、それのコーディネートによって本人のかっこよさが決まる…なんかもう、だからどうしたって感じの仕掛けがある。いや、本当にだからどうしたの?
そのかわりと言ってはなんだけど、今回はストーリーが結構凝っている。前作も前々作も凝ってたけどね。
あ、また例によって盛大にネタバレもするので、未プレイの人は見ない事をおすすめします。
まずね、導入部でボスと戦ったりしている。わりと物語の途中から入ったみたいで、不思議な雰囲気の始まり方だ。しかも、そのボスには豪快に負ける。なんてこった。
その後、画面暗転後はなにやら目を覚ますのだが、普通にどこかの村から話が始まる。主人公は一緒なんだけど、いまいち話が繋がっていない。ボスとの戦いはどこへ行ったのだろうか?
どうやら、導入部で出てきた主人公がそのまま主人公らしいのだが、話がつながっていない。夢? 記憶喪失? 生まれ変わり?
そして、主人公は序盤に穴に落ちて「もう一つの大地」に行ってしまうという事件が起こる。この、もう一つの大地が、今回のサブタイトルである「幻の大地」と言う話になる。一般には、元いた大地を上の大地、幻の方を下の大地と呼んだりする。で、この上下の大地を、穴やら井戸やらで行き来しながら、話を進めていく事になる。
で、ネタバレをすると、実は上の大地の方が幻で、下の大地が現実世界である。上の世界は何かと言うと、現実世界の人たちが見ている夢の集合体みたいなものらしい。だから、上の大地に住んでいる人々や、町などは、下の大地の誰かが見ている夢なのだ。
よって、主人公自体が夢なのかというと、それは少し違い、現実世界で冒頭のボスとの戦闘で肉体を封じ込められ、意識だけ夢の世界に飛ばされた、という設定になっている。それで、こんなような話になっているわけだ。
ゲームを進めるうち、最初にボスであるムドーと戦った仲間、ハッサンとミレーユとも合流し、また自分の肉体を取り戻し、生身の体のまま現実世界と夢の世界を行ったり来たりして、色々謎を解いていったりする事になる。
夢というのがゲームの一つのテーマで、それを考えると色々面白い。
上の大地は、下の大地の誰かが見ている夢なので、良く探すとその「誰か」が見つかったりする。ああ、この人のこんな夢が、上の大地のこういう事に繋がっているんだ、というのが多々ある。
一番分かりやすいのが、上の大地にも下の大地にあるレイドック王国で、上の大地でのレイドック王は、24時間一睡もしない、眠らない王様という設定である。やがて真相が分かり、下の大地でのレイドックに行くと、そこの王様は寝たきりで全く起きない、という事が判明する。なるほど、現実世界の本人はずっと眠っているために、夢の世界での王様は眠らないんだ、と分かる。
このへんは、ゲーム全体のシナリオとは特に関わらないところまで細かく作ってあり、さすが堀井雄二と思わせる部分がある。
さて、ゲームシステムは最初にも書いた通り、3や5などのシステムを組み合わせたようなものになっている。キャラクタは4や5などのように、固定ではあるが、ダーマの神殿があって3のように転職が可能になる。
基本の職業は、戦士、武闘家、魔法使い、僧侶、踊り子、盗賊、魔物使い、商人、遊び人である。3に比べると、いくつか増えている。また、勇者というのが基本職業としては存在しない。
魔物使いは前作5の主人公のようなもので、戦闘終了後にモンスターを仲間にする事が出来るようになる。盗賊は非常に便利な職業で、「とうぞくのはな」という特技を持っており、これを使うとダンジョンや町のそのフロアにあといくつ宝物が隠されているか、知る事ができる。これは大変助かる。いちいち全部のツボ、タルなどに「しらべる」をやって小さなメダルを探していた4以降のしちめんどくさいシステムが、多少マシになった。少なくとも、「もうこの階は調べなくていい」という事が分かるだけで、だいぶ楽になる。そしてまた、新しい呪文のレミラーマで、何かが隠されたツボなどを探り当てる事ができるので、いよいよ小さなメダル探しが楽になった。ここまでやるなら、もう後は「自動的にその町の全てのアイテムをかき集めてくる」呪文を搭載して欲しい。いちいち「しらべる」やるのはもう面倒くさすぎる。
で、基本職業の上に、上級職というのがあるのが、今回の転職システムの特徴。
今回は、主人公の基本的なレベルの他に、その職業自体のレベルというものが存在する。職業レベルを上げる事によって、その職業特有のスキルを覚えていくというシステムだ。魔法使いや僧侶なら呪文、戦士なら戦闘用の特技と言った具合に。で、複数の基本職の職業レベルをマックスまで上げる(これをマスターすると呼ぶ)と、上級職に就くことができる。例えば、戦士と武道家をマスターすると、バトルマスターという上級職に転職する事が可能になる。
この上級職の一つが「勇者」で、主人公の場合は上級職のどれかをマスターするとなる事かできる。一応他のメンバーでもなれるが、その時は4つの上級職をマスターしないといけないので、条件が厳しい。
この転職システムは、なかなか面白かったとは思う。FFシリーズなどのように、本人のレベルと職業のレベルが切り離されたため、ウィザードリィのような大幅なペナルティを伴う転職とは違い、簡単に職業を切り替える事ができる。また各職業のマックスレベルが8で、そんなに延々やり続けないとマスターできないようなものでもないので、複数の職業を渡り歩いて自分の好みのキャラにできるという楽しさはある。
ただ、職業ごとの経験値(熟練度)というのは、本人のレベルが上がってしまうと、雑魚からは得られない仕組みになっており、同じところでずっと戦っていればいいというものではない。しかしこれには抜け道があり、たいして強くもないのに内部レベルは高い(つまり主人公たちのレベルが上がっても熟練度が入る)敵というのがいて、それを探し出してそこでしつこく戦うのがベストである。
さて、この転職システムだが、面白い試みである反面、つまらない部分もある。
一つは、特技があまりにも強すぎて、ゲームバランスが壊れてしまっている事だ。
特技というのは、魔法ではない特殊なスキルの事であり、実質的な効果は魔法なのだが、呪文と違ってMPを消費しないという素晴らしい利点がある。
素晴らしいのだが、素晴らしすぎて他のスキルを使う要素がほとんど無いのだ。私は、結局全てのキャラクタに、スーパースターという上級職の持つハッスルダンスという特技と、隠し職業であるドラゴンのもつ輝く息という特技を身につけさせた。ハッスルダンスは、パーティ全体回復の効果がある。輝く息は、敵全体に対する大ダメージのブレス攻撃である。そして、私は毎ターン、一人がハッスルダンスで残りが輝く息(あるいは他の攻撃用特技)を使わせていた。
こういうのもどうなんだろう。実質魔法のようなものなのに、MPを消費するなどの仕組みが存在しないため、使い放題だ。よって、戦略性も何もなくなる。全て全体攻撃、全体回復である。また、キャラごとの個性もない。いかにも強そうなハッサン、賢そうなチャモロであろうと、攻撃は全体ブレス、減ったらハッスルダンスである。本当、こればっか。
そういうわけで、この転職システムのおかげで、ドラクエ6の戦闘バランスは破綻していると言っていい。また、この特技システムはこれ以降のドラクエにも搭載されており、全く同じバランス崩壊を招いているので、「特技のおかげでドラクエがダメになった」と批判する人は多い。
それともう一つ、これはドラクエ3にも通じる事だが、転職システム特有の欠点もある。これは、はるか昔3のレビューを書いた時に、「6の時に」と書いたので、ここで論じる事にしよう。
大筋は3の時にも書いたが、やはり転職によってスキルや特性が付与される以上、そこに何も制限が無ければ、最終的には全て同じキャラになる。全ての職業をマスターし、全てのスキルを使えるようになったキャラクタだ。こうなってしまえば、キャラの特徴もへったくれも無い。全部のキャラはただの記号となってしまう。
それが嫌なら、自分で縛りを入れればいいのだが、やはりシステム上可能になっている以上、やってしまうというのが人情だ。このへんの考えが、私と堀井雄二とで違うのかも知れない。
私は、「小さなメダル」システムも好きではない。いちいち町のあちこちを探してまわるのがただの作業であってゲームとしては面白くないからだ。しかし、「嫌ならやらなきゃいいじゃん」と言えば、それもそうである。が、システム上できる以上やってしまうのが人情。カジノもそうで、シナリオが盛り上がってきたところでカジノで時間取られるのは嫌なんだが、システム上そこで頑張った方がメリットがあると分かると、嫌でもやってしまう。
話を転職に戻すと、以前にも書いたが、キャラのイメージ上の個性が無くなるというのも嫌だ。例えば、こいつはゴツイから戦士系と頭の中でイメージしていても、そのうち魔法使いや僧侶などに転職してしまうとイメージがどんどんボヤけていく。このドラクエ6はまだキャラのイメージが固定しているからいいようなものの、ドラクエ3や、もともとのウィザードリィの事を考えると、キャラの絵などは無いので、自分で考えないといけなかった。「こいつは最初戦士系だったけど、魔法使い、僧侶となり、賢者となってそのあと勇者になった」みたいなキャラクタをどうイメージすればいいか分からなくなる。
このような、キャラの個性とカスタマイズ性の問題は、別にドラクエだけの問題ではなく、他のFF等にもある。自由で、なんでもできるというのは楽しい。しかしそうなっていると、全部やってしまう。最強、最高効率を目指してしまう。その結果、キャラが全て記号化してしまい、思い入れも何もなくなってしまう。スーパーキャラ1、スーパーキャラ2になるだけだ。
ま、このへんは好き嫌いの問題なので、別に誰でもこう感じるはず、という批判ではない。こうなっている方が面白いという人も当然いるだろう。ただ、私としては、もう少し制限をつけて、キャラに特徴付けられる方が良かったなと思う。
システムの話はこれくらいにしておこうか。
私はこのゲームを、弟と二人で折半して買った。当時私は色々忙しかったので、弟が先にプレイして、私が後からやったっけな。珍しく。
途中までは普通にぽつぽつ進めていく感じだったが、途中から「む、これは…?」とシナリオのある点が気になり、その先が早く知りたくて物凄い勢いでゲームを進めた記憶がある。
そのある点というのは、結果から言うと勘違いだったのだが、このドラクエ6のマップが、旧三部作のロトシリーズのマップとちょっと似ていると思ったのだ。特にドラクエ2の全体マップと。どっちを勘違いしたんだっけな。上の大地かな(注:結果的に勘違いだったので、実際には全然似ていません)。
となると、6はどうやら4、5と繋がっているらしいので、例えば1〜3は4〜6の世界から見ると「夢」という位置づけになるとか、あるいは単純に6の現実世界が1〜3と繋がっていて、4と5が実は夢とか、そういう事を示唆しているのかな、と考えたわけだ。
こうなると先が気になってね。6自体は、マスタードラゴンが出てくる関係で、4や5と世界観を共有しているのかなというのが分かるが(ただし天空シリーズが無いので、微妙なところ)、ダーマの神殿やルビスなど、旧三部作の要素も出てくるわけで、この作品のテーマが夢であるという事はここで一つの大きな繋がりが分かるんじゃないか、とワクワクしたわけだ。
が、まあ全然そんな事は無かった。マップが似ているというのも勘違いだし、結局旧三部作との繋がりは全く見つからなかったし、それどころか4や5との繋がりも分からない。
かつてドラクエ3の時に、1や2の世界を説明する大掛かりなシナリオが描かれたので、もし4〜6をまた三部作とみなすとすると、6で謎が明かされるのではないかと期待したのだ。
…期待しすぎたよ…。がっくり。
ま、旧三部作との繋がりについては、私が勝手に期待していただけだからどうでもいいけど、せめて4・5・6のそれぞれの繋がりがどうなのかは明らかにして欲しかったかな、と。
全体を通していくつか批判的な事は書いたが、ゲームとしてはつまらなかったわけじゃない。ただ、その批判した部分である特技による戦闘バランスは最後まで気になったし、従来の作品に比べて大きなシステム変更等は無かったので、私の中ではインパクトの少ない作品になってしまっているかな、と思う。ドラクエの中では。