| メーカー | エニックス | 発売日 | 1994-11-25 |
| 機種 | スーファミ | ジャンル | サウンドノベル |
| 評価 | ★★☆☆☆ |
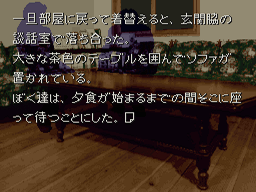
|
「弟切草」に続く、サウンドノベル第二弾。昔懐かしい、殺人事件の犯人を捜したりするアドベンチャー。まるで小説のような展開は、懐かしくもあり新しくもあった。 |
●
釜井達の夜だって?
まず、エニックス(チュンソフト)はこのゲームに先立ち、「弟切草」という作品を出していた。それが、サウンドノベルシリーズの第一弾である。言ってみればただのアドベンチャーなんだけど、テキストを画面一杯に表示するのが特徴である。グラフィックは、その下の背景として表示されている。小説を目指しているらしい。それに音がついているので、サウンドノベルなんだそうだ。
「かまいたちの夜」は、そのサウンドノベルシリーズの第二弾という事になる。今回も名のあるシナリオライターをつれてきて、殺人事件の推理物アドベンチャーに仕立てている。
ゲームシステムとしては、説明文として表示されるテキストや、その背景をグラフィックを見ながら順送りしていき、時々出てくる選択場面で、適当な答えを指定して分岐していく、というものである。
PCでは長いアドベンチャーゲームの歴史があるが、「ポートピア連続殺人事件」や「ミオのミステリーアドベンチャー」などからは、自分で自由に場所を移動し、そこでのコマンド選択でフラグを立てていくというシステムになっている。ひたすら分岐を重ねていくという手法は、それよりも前の世代の仕組みである。非常に古典的な仕組みのゲームと言えよう。もちろん、当時のPCをはるかに越える容量を扱えるので、単に分岐式と言っても次元の違うゲームを作れているのだが。
特徴的なのは、ちょっとした分岐の違いで、シナリオが全然違うものになってしまうという事だ。
このゲームの大まかなストーリーは、主人公とその彼女が訪れたペンション(全体として密室状態にある)で、殺人事件が起こるというもの。だから結局、その犯人をつきとめないといけない。
ところが、途中での分岐の仕方により、犯人が変わってしまう事もあるのだ。いや、そもそも殺人事件が起きないケースだってある。それ以前に、ペンションにすらたどり着かないルートもある(確か…うろ覚え)。
ただ、それらの派生ルートの結末は、バッドエンディングである。真のエンディングを迎えるためには、シナリオライターが想定している真犯人を推理した上で、そいつが犯人になるようなルートをたどるしかない(というか、ルートをたどる事さえ出来れば、別に推理なんか必要ないのだが)。
まあそんな感じで、豊富な容量をいかし、太古の分岐式アドベンチャーでは作りきれなかった新しい形のゲームになっている。
ここで苦言を二つほど。
(ここからシナリオに関するネタバレがあるので、気になる人は飛ばすように)
まず、トリックについて。シナリオは、純推理小説のように良く出来ている。しかし、良く出来ているがゆえに、納得のいかない部分が出てくる。
今まで書いたとおり、ペンションで起きた殺人事件を解くのがゲームの目的である。で、例によって凶器がどうとか、アリバイがどうとか、殺人の手法がどうとか、色々情報を集めて犯人を追い詰めていく。
それでまあ、これはアドベンチャーのお約束で、こちらの推理とは関係なくゲーム上の主人公は自問自答しながら考えていくので、正しい選択をしていけば真のエンディングに到達する。ところがそれが非常に納得いかないのだ。
というのも、途中で手に入れた情報を総合的に分析すると、犯人がいなくなってしまうのだ。全員アリバイがあるとか、殺人が不可能とか、そんな感じでね。でも真犯人そのものの目星はついているので、問題はそいつがどういうトリックを使ったかになるのだが、これがどうしても解けない。
それで真のエンディングでの説明がどうなっているかというと、結局その犯人は、物語の途中で「これは出来ない」と言及されているある行為をしているのが判明するのだ。ネタバレになるので具体的な話は避け、架空の話で説明すると、「14:20発の電車は無いから、彼が15:00にここで殺人を行うのは無理だ」という説明がゲーム中でなされるのに、真犯人判明後の説明で「実は14:20発の電車に乗った」と言われるようなものだ(もちろんこんな直接的な形ではなく、ボヤかされてはいるが)。
私は兄弟とこのゲームを遊んでいたのだが、クリア後には「これは卑怯だ」という批判が当然ながら出た。作品中で「出来ない」と言われているから、その可能性を排除して推論を組み立てていたのに、最後に「やっぱり出来ます」と言われても、到底納得は出来ない。そんなようなゲームなのだ。
なまじ、状況の設定などが純ミステリー風になっているだけに、ここはゲーム全体をぶち壊す要因だと思った。
もう一つの苦言は、ゲーム中にはさまれるギャグだ。
先ほど書いた通り、このゲームは非常に古いタイプの、選択肢で分岐していくアドベンチャーゲームだ。で、流れによって全く違った展開になる。
で、本筋の、つまり真犯人が殺人を起こすというシナリオ以外の横道ルートは、往々にしてギャグルートになる。しかもそのギャグセンスが、非常に古いというか、くだらないダジャレレベルの物を大げさにしたような感じなのだ。で、本筋以外がこれという事は、細かいルートの多くがこのギャグルートという事になる。従って、色んなルートを複数回やった印象としては、まじめに殺人事件を推理するゲームというより、下らないギャグを見せ続けられるゲームという雰囲気になってしまう。
これはちょっとどうかと思うねえ。これが面白いと思ったのかな。真剣に推理アドベンチャー作るなら、横道のシナリオもそれなりの物にすべきだ。製作者はこの雰囲気も含めて楽しんで欲しいと思ったのだろうが、どうにも私はそのノリにはついていけなかった。
と、まあいくつか文句をつけはしたが、こういう「殺人事件を解く」的なアドベンチャーゲームをやったのは久々という事もあって、実際楽しませてもらった。なんだかんだ言って全ルートの分岐を調べたりとか色々細かい事したしね。
上記の不満点を除けば、まずまず楽しいゲームだった、と思う。