●
その他
その他の機種をまとめて。
<PC>
●イース2 (日本ファルコム 1988-04)
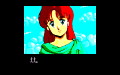
-
大人気だったイースの続編。主人公は一緒だが、舞台が異なる。特徴は、アニメーションの演出をかなり取り入れた事で、オープニング等で見られるヒロインの振り向きアニメなんかは、その手の人たちの心をわしづかみにした。
●スタークルーザー (アルシスソフト 1988-05)
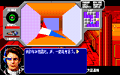
-
来た。わりと一部の人の中では伝説になっている、まさに「隠れた名作」の一つ。当時にしては珍しい、ポリゴンを多用した宇宙冒険ゲーム。私はこれと同じような雰囲気のゲームを(もちろんこのゲームを知る前に)MZ2000で作ろうとして、挫折した。
●ARCUS (ウルフチーム 1988-05)
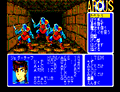
-
ま、この頃は大量に出ていた、ごくごくオーソドックスなRPGではあるんだけど、キャラクタを前面に押し出したのが特徴。この時期の日本のRPGは、元々の洋物RPGから離れつつあり、その一つの象徴が、このようなオタクアニメ風のキャラ、世界観を持ったゲームだった。
●琥珀色の遺言 (リバーヒルソフト 1988-06)

-
推理アドベンチャーの雄、リバーヒルソフトの作品。大正時代を舞台にしており、雰囲気を高めるためか全編がセピア色で統一されている。当時の色数の少ないPCでは、これがかえって表現力を高めており、かなり高い画質を誇っていた。
●ラストハルマゲドン (ブレイングレイ 1988-07)

-
RPGのタイトル数があまりにも多いので、この頃は「ちょっと目先を変えよう」というゲームが多かった。これもその一つで、プレイヤーキャラが全部モンスターというのがその特徴。他のRPGではやられキャラになっている各種のモンスターを操って戦っていく。
●エグザイル (日本テレネット 1988-08)
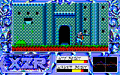
-
テレネットの好きそうなARPGなんだが、なんと中世イスラム世界が舞台。シーア派の暗殺集団の一人となって、セルジューク朝のカリフを殺すのが目的というから死ぬほど本格的。「アサシン」の語源がハシシ(大麻)だという事を知っている人もいるかも知れないが、それを証明するかのごとく、主人公は麻薬を使いまくる。他RPGでいう薬が、麻薬になってる感じ。全体的に凄すぎた。
●マスターオブモンスターズ (システムソフト 1988-10)

-
これもモンスター物。同社が手がけている大戦略シリーズをベースに、ユニットをモンスターにしたというもの。主人公はサマナー(召喚士)で、敵サマナーとモンスターを召喚しあって戦う。変に現実世界に縛られてない分、良いゲーム化が出来ていたのではないかと。
●サイオブレード (T&Eソフト 1988-11)
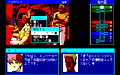
-
ハイドライドなどで有名なT&Eが出したSFアドベンチャー。売りは、アニメを多用した映像表現。ブラスティ以降、PC-88でも頑張ればアニメが出来るという事で、こういう作品も出た。見た目でなく、やった人の中では結構ゲーム内容の評判も高い。
●スナッチャー (コナミ 1988-11)
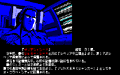
-
アーケードやファミコン、そしてMSXなどでゲームをリリースしまくってるコナミが、珍しくPCオリジナルの作品として出したSFアドベンチャー。はっきり言って、映画「ブレードランナー」の劣化コピーのようなシナリオ。これは監督(笑)の趣味だろう。詳しくは別機種版の時に。
●ウィザードリィIV (アスキー 1988-12)
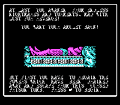
-
またもやモンスター物。考える事一緒すぎ。このゲームの主人公は、なんと第1作のボスだったワードナ。人間の手で倒された彼は、迷宮の奥で復活を果たし、モンスターを仲間にしながら地上を目指す。当然、敵は人間ばかり。シリーズの中でもかなり異端の作品。
●信長の野望 戦国群雄伝 (光栄 1988-12)
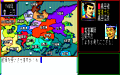
-
前作からの大きな進化は、配下に武将を持つ事が出来るようになったこと。今までは主人公=一人の武将という事で、国の数しか武将がいなかったけど、今回は一国に多数の武将がいる事になる。それぞれの武将を育てて使う事ができ、歴史オタもかなり満足さ。
●ドラゴンスピリット (電波新聞社 1988-??)

-
X68000用に電波新聞社が移植したもの。出来は素晴らしく、アーケードそのままと言っても過言ではない。縦画面モードと称し、アーケードと同じくモニタを90度回転させて使うモードもあった。ローディング画面に工夫があったり、芸が細かい。
●源平討魔伝 (電波新聞社 1988-??)

-
これも電波の移植。やっぱり出来は良い。良すぎる。かなり遊ばせてもらいました。
<MSX>
★ウルティマEXODUS (ポニカ 1988-05)
●クリムゾン (クリスタルソフト 1988-08)
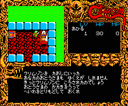
-
PCからの移植なんだけど、だいぶドラクエの影響も入っている、オーソドックスなRPG。で、今でも記憶に残っているのは、「ペガサスワープ」と「キグナスワープ」という、二つのワープ方法。二つと言っても差はないんだけど、とにかく自分が設定した場所にいつでもワープできるという仕組み。結構面白かった。
●イシターの復活 (ナムコ 1988-09)
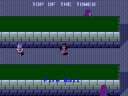
-
MSX2専用で、パッと見た感じ移植度は完璧。良くもここまでと思うくらい、アーケード版を再現している。ところが、この画質を得るためにキャラなどを全てスプライトではなくグラフィックで描いており、従って死ぬほど重い。コマ落ちしまくりだし、動作も鈍い。正直やってられなかった。
<セガマークIII>
●スペースハリアー3D (セガ 1988-02-29)
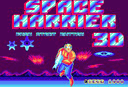
-
マークIII独自の続編。立体視スコープを利用する事により、画面が立体的に見えるというのが売り。なかなか楽しめた。ただ、マークIIIというハード自体にもう無理があった。
●天才バカボン (セガ 1988-06-02)

-
この頃はなんだか血迷ったゲームが色々出てたなー。奇面組のゲームなんかも出てたし。原作関係ないだろ。このバカボンもそんな感じ。不条理アドベンチャーなんだけど、途中奇妙なシューティング面になる。これがかなり難しい。
●魔王ゴルベリアス (セガ 1988-08-14)

-
コンパイルがMSXで発売していたものの移植かな。ARPGなんだけど、地味な見た目とは裏腹に、結構面白い。面白い…という記憶だけ残っていて、あとほとんど忘れている。クリアしたかったけど出来なかった記憶もある。
●イース (セガ 1988-10-15)

-
言わずと知れた例のあれ。移植の度合いは結構いい。少なくとも、ファミコンよりはずっとマシだろう、と言われていた。
<メガドライブ>
★スペースハリアーII (セガ 1988-10-29)
●獣王記 (セガ 1988-11-27)

-
一応アーケードの移植作。主人公がパワーアップすると、獣になって特殊能力が使えるという横スクロールアクション。石化ブレスを吐く熊が一部でかなり人気。でもゲームとしては、どこを楽しめばいいのか分からないような気の抜けた作品だった。セガはこんなゲームが多すぎる。単に作っただけって感じ。
<PCエンジン>
●邪聖剣ネクロマンサー (ハドソン 1988-01-22)

-
H.R.ギーガーのイラストがインパクトを強めている、おどろおどろ系RPG。適当に仲間を見繕って出かけ、ひたすら戦いまくる。血とかたくさん出る。聞いた話によると、このパッケージイラストになってるギーガーの絵だけど、承諾も何も取らずに勝手に使っているらしい。マジかよ。
●R−TYPE I・II (ハドソン 1988-03-25, 06-24)
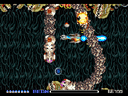
-
アイレムの同名ゲームをハドソンが移植。見た目等は非常に良く移植されており、遜色ない。ただ、当時のいわゆるHuカードにはおさまりきらなかったので、4面までと5面以降で別ゲームとして発売する事にした。そんなのありか。
●No.Ri.Ko. (ハドソン 1988-12-04)

-
PCエンジンは、早くもこの時期にCD−ROMを本体の拡張機器として発売している。このゲームはそのさきがけ。アイドル小川範子を使ったなんつーかこの微妙なゲームらしい。1回くらいしかやった事がない。今度はクリアオフをやろう。
●ファイティングストリート (ハドソン 1988-12-04)
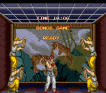
-
カプコンのアーケード版「ストリートファイター」の移植。なぜタイトルの前後を入れ替えているのかは不明。相変わらず絵は良く移植されている。ただ、2ボタンパッドなのでどこかしらに問題は出てくる。裏技で、セレクトとか押しながらボタンを押すと必殺技(波動拳など)が簡単に出た。
その他に1988年に発売されたゲームとしては、以下のような物がある。
<PC>F15ストライクイーグル、アルギースの翼、プロフェッショナル麻雀悟空、ファンタジーIII、バーズテイル、A列車で行こう2、アンジェラス、ザ・スキーム、テトリス、アドヴァンストファンタジアン、マイト&マジックBook2、エグザイル2、シュヴァルツシルト
<PCエンジン>パワーリーグ、ファンタジーゾーン
ファミコンの爛熟期ではあるが、少々マンネリ化というか、粗製濫造的なソフトも増えてきた。アーケードにおいても同様で、続編が多く、いまいちインパクトに欠ける印象があった。
そんな中、前年のPCエンジンとそしてこの年のメガドライブは、家庭用ゲーム業界に変化をもたらせようとしていたと言える。