| メーカー | エニックス | 発売日 | 1990-02-11 |
| 機種 | ファミコン | ジャンル | RPG |
| 評価 | ★★★★☆ |
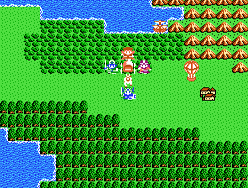
|
超人気RPGの第4弾。ストーリー的には仕切りなおしになったが、ラスボスの視点も含めて語られる話はなかなか良い。 |
●
頑張れピサロ
90年代最初に取り上げるゲームは、あの大人気RPGの続編である。
IIIまで年1回のペースで出ていたドラクエだが、このIVは前作から2年空いていた。もちろん、IIIまでの高い人気を引き継ぎ、大変良く売れた。
ゲーム内容は、IIIからは大きく変化している。
まず、転職による自由なキャラメイクが売りだった前作とはうって変わって、キャラクタは固定である。主人公である勇者以外は、固定のキャラクタを仲間にする事になる。そして以後このスタイルが定着したので、結局キャラメイク可能だったドラクエはIIIだけという事になる。
また、章立てになっているのも、従来までとは大きく違う点だ。このIVは全5章構成になっていて、しかも主人公である勇者はその第5章まで出現しない。4章まで、それぞれ異なった主人公で物語を進めていき、最後の章で集結する。「導かれし者たち」というサブタイトルは、まさに中身を言い得ている。
もう一つこのIVの大きな特徴と言えば、いわゆる「AI戦闘」が挙げられる。第5章では、勇者以外のキャラクタは戦闘時は自動的に行動する。今でこそ自動戦闘は当たり前だが、このIVの時はセールスポイントとして大々的に打ち出していた。なんでも、キャラクタの思考ルーチンは戦闘を重ねるごとに進化していく、だからAIなんだそうだ(とても疑わしいが)。
世間的にIIIが傑作と見なされているという事は前回書いたが、その分IVはIIIと比較すると低い評価を受けている部分がある。しかし私は、どちらかと言うとこのIVの方を高く評価している。私の兄弟も、IVは気に入っているようだ。
私がIVを評価しているのは、IIIで感じた大きな欠点を克服してきているからだ。
まず、IIIではそれまでより話が大幅に長くなっていた。アリアハンから始まり、バラモスを倒してアレフガルドに至る、という感じでかなりのボリュームのお話になっている。別につまらないわけじゃないのだが、やや中だるみするところはあった。作者が目指すところまで持っていくには、それだけの長さが必要だったんだろうけど、やっぱり冒険の途中で少し息切れする部分があり、「もうちょっと波が欲しいな」と思う部分が正直ある。
ところがIVでは章立てになっており、章を1個ずつ進めるたびにキャラを育てていくので、中だるみがなかった。さすがに第5章はかなり長いんだけど、シナリオが面白いし、それにそれまでの章で訪れた町などに行くと話の経過がわかるので、飽きさせなかった。あと、最終的にはそれまでの章に出てきた7人の仲間たちが集結するのだが、その中から4人を選んで戦闘に参加させる仕組み(馬車システム)なので、とっかえひっかえしながら楽しむという遊び方も出来た。ここは戦士系多めにとか、回復系二人連れて行こうとかね。
そんな感じで、色々と中だるみさせない工夫があった。
もう一つIIIで感じた欠点として、仲間の無個性化があった。
IIIの、ウィザードリィライクなキャラメイク&転職システムは、確かに楽しかった。しかしその反面、一人一人のキャラクタに思い入れがなくなってしまうという欠点もある。
キャラクタを作ってるのだから、背景設定や性格などがなくなってしまうのは、仕方ない。私が言いたいのは、戦闘時の特徴などがなくなってしまうというところ。普通RPGでは、「こいつは素早いけど防御力が無い」とか、「こいつは魔法が使えるけど体力が無い」とか、様々な個性をもったキャラクタ達を使ってうまく戦闘を進めていくところに醍醐味がある。しかし転職可能なゲームだと、そういうキャラの弱点を消していく形で転職させるので、結果的に個々の特徴がなくなってしまう。じゃあ転職させなければいいじゃんと言うかも知れないけど、システムで許されてるのにわざわざ自分で縛りを入れるのも味気ない。
同様の欠点として、例えば「こいつは魔法使いね」と決めて、魔法使いっぽい名前にし、自分の脳内ではそういうイメージのキャラクタにしているのに、戦士に転職させてしまうと、なんだかイメージと外れてしまう。しかし最初からそれを見越して戦士っぽい名前にしておくと、最初の魔法使い時代に違和感が大きくなる。結果として、自分の脳内パーティなんかを想像してても仕方ないので、キャラがどんどん記号化してしまう(これはウィザードリィでもそうだったね)。
このIVでは、キャラは固定されており、しかも転職などでスキルが変更しないので、個性としては大変に強い。アリーナ姫は最後までパワーキャラだし、マーニャは最後まで馬鹿魔法使いだ。単に名前や設定だけでなく、戦闘時の特徴で個性を表しているのは、大きく評価できる(これはのちのDQやFFへの批判でもある)。
さて、このIVのシナリオだが、実はIIIまでとは関係が無いらしい。以前、ドラクエI〜IIIまでが一つの大きなストーリーを形成しているのを賞賛したが、そのお話は一応IIIで完結という事になり、IVからはまた別の新しいお話になっているようだ。これはちょっと寂しかったけど、仕方ないか。
ちなみに、IIIまでは「ロト三部作」と呼ばれ、またIV以降は「天空シリーズ」などと呼ばれている。「天空の城」や、「天空の剣」などの「天空」関係が共通点になっているからだ。
そのように、IIIまでとは切り離されているのだが、IVのシナリオはかなり良く出来ている。
まず、全5章に分かれている事は前述したが、うち最初の4章は、最後の章で勇者の仲間になるそれぞれのキャラクタの物語を描いている。
一章あたりはあまり長くないのだが、一つ一つの章が上手くシナリオ全体のテーマを取り上げているのが面白い。
例えばライアンの章は、子供の誘拐事件を取り上げており、これが「敵がまだ子供である勇者を探している」ということを表している。次のアリーナの章は、ラスボスになるピサロとの絡みを描いていく。3章のトルネコは天空の装備をテーマにし、最後のマーニャ・ミネアの章では、ストーリー全体のキーである「進化の秘法」について語られている(進化の秘法は2章でも関係してくる)。
これらの話がバラバラに語られたあと、最後の章で一つのストーリーにまとまっていく。この手法、およびシナリオそのものは、私は大変に高く評価している。
シナリオ上の面白さで言えば、ラスボスになるピサロがかなりシナリオに絡んでくるのも興味深い。
そもそも、ドラクエもI、II、IIIと回を重ねるごとに、ラスボスのインパクトが薄れていった感がある。初代の竜王のインパクトはかなり強かった。最初から竜王を倒す事が唯一の目的だったし、各地で竜王の強さが語られ、竜王を倒すための装備としてのロトの剣等を集めるというお話になっていた。IIのハーゴンはまあそれなりのインパクトがあったが、しかし物語が複雑化するにつれ、最後の目的であるハーゴン討伐というのを忘れる時間がかなりあった。IIIに至っては、ゾーマの存在が終盤まで隠されているし、シナリオに絡んでこないので、思い入れがあまり無い。
ピサロは、第2章で始めて登場し、プレイヤーに存在を焼きつけていく。もっとも、最初はその姿を見る事が出来ないのだが(このへんも期待を持たせる演出でなかなか良い)、それまでの「最後まで出てこない謎のボス」ではなく、積極的に物語に絡んでくるボスで、新鮮でもある。
また、単に「悪だから」という理由でボスになっている奴らと違い、ピサロははっきりと人類滅亡を志しており、ロザリーヒルでの物語でその理由もわかるようになっている。むしろそのお話が悲しすぎて、ビサロには共感を抱いてしまう。つーか、ピサロ頑張れ! 人間なんて滅ぼしちゃえ!
…取り乱してしまった。とにかく、ジョジョで言うところのディオみたいに、最初から物語に参加してくるラスボスというのは、私はとても好きだ。
あと珍しいのは、途中でデスパレスという魔物の城に潜入するイベントがある。変化の杖を使って魔物に化けるんだけど、当然出会うのは敵の魔物ばかり。話も出来る。前作までは、モンスターと言えば単に野生化してそのへんをうろついている化け物って感じだったけど、このデスパレスでのイベントを見れば、きちんとした軍団組織を作り、話し合いとかをしてるんだなーというのがわかる。
もう一つ面白いのは、5章の途中、鉱山都市アッテムトで地獄を掘り出してしまう事件。あまりに深く坑道を掘りすぎて、中にあった地獄に通じてしまったのだ。
この事件はわりと偶然に起こり、またここには地獄の帝王エスタークがいるのだが、実はエスタークはラスボスではない(もちろん本当のラスボスはピサロ)。ではないのだが、しかしこの事件は物語に大きく関わっていく。
こういう風な、リアルタイム性のあるイベントはこれまであまり無かったので、斬新でもあるし、またこの前後に先ほど書いたデスパレス、そしてロザリーにまつわるイベントがあるので、強烈な印象をもたらしている。
他にも印象的な話はいくつもある。色々な伏線があるんだよね。ピサロや天空の城の話もそうだし、あるいはアリーナ姫のサントハイム城の住人がいなくなる事件、勇者の村で最初に起こる住民虐殺事件、その近くの山小屋に住んでいるきこり、マスタードラゴンの話、世界樹とエルフの話など、まあ様々な要素が組み合わさり、完成されたシナリオを構築していた。
全く、ファミコンレベルでは信じられないくらい良く出来ていると思う。
あとは、細かい遊びもいくつか取り入れられており、シナリオとは関係のないところで楽しめるようになっている。
まず、3章では商人であるトルネコが主人公なんだけど、色々とお金稼ぎを要求される。最初は武器屋の店番で、人から武器を仕入れたり、売ったりして稼いでいく。ゲームとは言えないくらいのちょっとしたイベントなんだけど、なんだか独特の雰囲気があって面白い。
それから、カジノが前作に引き続き存在する。今回は、ポーカーが出来るのが売り。いわゆるスロットポーカーで、ダブルアップで稼ぐ事ができて、結構熱い。これだけでかなり熱中できる(もっとも、私は本質的にはカジノには反対しているのだが)。
あと、今回から「小さなメダル」システムが導入されている。これは、宝箱やツボ、あるいは他人の家の中などに存在する「小さなメダル」というものを集めると、あとでメダル王からいいものと交換してもらえる、という仕組み。
この小さなメダルシステムは、このあとドラクエシリーズ全部で搭載されているんだけど、私はあまり好きではない。確かにメダルがたまってくると嬉しいんだけど、それを見つけるために、目に見える全ての物を調べないと気がすまなくなってしまう。これは作業をやらされてる感がちょっとあって、私の中でも賛否両論というか、功罪ともにあった気がする。
ちなみに小さなメダルで得られる武器に、「奇跡の剣」というものがあるが、これが凄く強い。敵にダメージを与えるたびに、自分の体力が回復していくというもの。ライアンあたりに装備させておくと、もうライアンの回復の必要はなくなる。うちでは「きせつる」と呼んで親しまれていた。
戦闘の話でもさせてもらおうか。
AI戦闘の話を最初に書いたが、それが導入されるのは5章だけで、4章までは従来どおりのマニュアル戦闘だ。
5章になって、ようやく自分で名前をつけた主人公(=勇者)が出てくるんだけど、この章での戦闘が、AIバトルになる。プレイヤーが直接操作できるのは主人公だけで、戦闘に参加している残り3人の仲間はオートで動くという仕掛けだ。
オートというからには、そのキャラなりの思考ルーチンを使って適当に戦うんだけど、一応指針というか、「作戦」という形で行動パターンを制御できる。作戦には、以下の種類がある。
| ガンガンいこうぜ | MPを気にせずにフルパワーで戦う |
| みんながんばれ | 標準的な作戦 |
| じゅもんせつやく | みんながんばれよりも呪文の使用頻度を下げる |
| いのちだいじに | 防御、回復を優先する作戦 |
| いろいろやろうぜ | 手持ちのアイテムや、あまり使わない呪文なんかを使う不思議な作戦 |
| じゅもんつかうな | 一切呪文は使わない |
一応、制作者としては「みんながんばれ」を主軸に、後は状態によって変化させていくというのを期待していたのではないかと思う。しかし実際には、多くの人は「じゅもんせつやく」からほとんど動かさないと思われる。何しろこの作戦が一番使い勝手がいい。あんまりに使い勝手が良すぎ、作戦を変える意味がほとんど無いので、あとの方のドラクエではこの作戦は残ってないくらいだ。
でもって、建前上AIである。AIというのは、学習機能があると喧伝されていた。
例えば、ある敵と戦うとする。最初はその敵の情報が何も無いので、適当に戦う。ここでは、「いろいろやろうぜ」を使うといいかも知れない。で、色々やってるうちに、その敵に効く攻撃などを発見し、最も効率の良い攻撃を仕掛けていく。やがて敵の最大HPなども判明し、安全かつ最速で倒すパターンを覚えていく…。
というのが、きっと制作者のやりたかった事に違いない。事前にもそんなように広告されていた。しかし、全然そんなのはできていない。大体、私は発売前から懐疑的だったんだけど、ファミコンの容量、そしてバックアップできる領域の大きさから言って、学習なんてまともにやれるはずが無い。
実際、キャラクタは最初から敵の強さをある程度知っているように見えるし、それに何が効いて何が効かないなんてちっとも覚えない。今でも語り草になっているんだけど、クリフトがザキやザラキなどの即死系魔法を、それらが絶対効かない敵に何度もかけたりする。もうね、学習機能搭載してくれよって言いたくなるよ。
何度か書いたとおり、第5章はAIバトルになり、仲間のマニュアル操作は一切出来なくなる。
この仕組みは、かなり評判が悪かった。特にそれまでのドラクエを愛好していた人からは嘆きの声が良く聞かれた。
やっぱね、自由が利かないというのは辛い。先ほど書いたとおり、クリフトは効きもしない呪文を唱え続ける。更に困るのが、効くと分かってる呪文、ここでこれを唱えて欲しいと思う呪文を全然使ってくれない事だ。特に、バイキルトが使えないのはきつい。バイキルトというのは攻撃力を増やす呪文で、ちょっと強い敵と戦う時には絶大な効果を発揮する。これをブライが覚えるんだけど、また使ってくれないんだ。ほんと、頼むから使ってよ。
そういうわけで、このIVで取り入れられたAIバトルシステムを批判する人は結構多かった。魔法や道具を上手く使って、敵の特性に合わせて戦うことに醍醐味を見出していた人は、コンピュータ任せの戦闘には耐えられなかったのだろう。
実のところ、私も最初にそのシステムを知った時には、「え〜っ」と思ったものだ。補助的に自動戦闘があるのはいいけど、それがメインでマニュアル操作が無いというのはきつい。やる前にはかなり批判的だった。
実際やってみての感想としては、思ったより悪くないというところだね。確かに自由に操れない事に対する不満もなくはないけど、そのAIの馬鹿さ自体を楽しめるようになれば、そこそこいけるかな、と。AIバトル自体には、戦闘がお手軽になるとか、あるいはダメージを受けたそのターンでの回復が出来るとか、メリットもあるしね。
ところで、このゲームで最高レベル(99)に達するのは簡単だ。恐らく、ドラクエシリーズの中で最も楽なのではないだろうか。
基本は、「メタルキング」を使った稼ぎ。キングスライムのメタル版なんだけど、当然経験値が高い。が、防御力等も高い。
以前紹介したとおり、前作ではドラゴラムを使ったはぐれメタル退治が使えたのだが、今回その手は通用しない。そのかわり、「聖水」による攻撃が異常に効く。聖水というのは元々トヘロス(エンカウント率を下げる呪文)の効果があるのだが、戦闘中に使うとほんの少し敵にダメージを与える。このダメージが実は敵の防御力無視なので、メタル系の敵にはすごく良く効くのだ。そこで、聖水を使ってメタルキングあたりを倒していると、あっと言う間にレベルが上がっていく。
だが、もっと簡単な方法もある。有名な技だが、必ず「かいしんのいちげき」を出せるようになるバグ技があるのだ。
その他、このゲームにはバグ技が多い。上記の技と並んで有名なのが、カジノでの裏技。カジノではメダルを現金で買って遊ぶのだが、特定の枚数(とんでもなく大きな数字)を入力すると、なんとそれが4ゴールドで買えてしまうのだ。これを使えば、もはやカジノでいちいちメダルを稼ぐ必要はなくなる。
他にも各種バグがあるのだが、まあこれはシリーズ伝統のご愛嬌といったところだね。
あと一つ、ユーザーインターフェースが地味に進化しているのも取り上げたいね。今までの作品も少しずつ進化していっていたのだが、このIVはかなり快適である。個々の作業に対するレスポンスが良くなっているだけでなく、例えばアイテムを渡す時、カーソルを合わせた相手の持ち物の内容を表示してくれるなど、全体的に情報量を上げる方向で快適さを上げている。IIIとやり比べてみると、あらゆる面でやりやすさが違う。
そんなわけで、快適なシステムと良く出来たシナリオ、飽きさせない章立ての構成などと様々な要素があいまって、私の中ではかなりの良作認定になっている。IIIである意味完成したシステムを、更にブラッシュアップしてきたのは偉いと思う。