| メーカー | ポニカ | 発売日 | 1988-05 |
| 機種 | MSX | ジャンル | RPG |
| 評価 | ★★☆☆☆ |
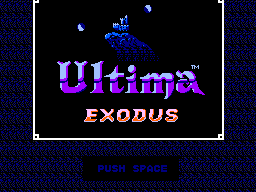
| PC版の名作「ウルティマIII」をMSXに移植。というより、ファミコン版の移植。子供向けの見た目とは裏腹に、中身はやっぱりウルティマだった。 |
●
アンブロシアに憧れて
元のシリーズで言うところの、ウルティマIIIである。それをファミコンでは「ウルティマ 恐怖のエクソダス」という名前で売り出したのだが、その移植版と言える。のちにポニーもPC版でI・II・IIIを発売したが、それまでPC版のウルティマと言えばスタークラフトの移植だったので、PCからの移植とは言いがたい。やはりファミコンからの移植だろう。
ちなみに、ファミコン版はPC版に比べるとややアレンジされているので、当然このMSXもそれに倣っている。
ウルティマIIIは、前作IIまでのマニアックな雰囲気を、ある程度一般向けにした感じはある。何しろ前作は、宇宙船で太陽系の他の星行ったりとかしてたし。
ただ、それもこれまでのシリーズと比較したらというだけの話であり、ドラクエ慣れした日本人から見れば、かなりクセのあるゲームと言って良い。今の私がやっても、なんだかわけがわからない。良くこんなゲームを当時は必死にやってたなー、と色んな意味で感動する。
シナリオは、また例によってロードブリティッシュに頼まれて世界を救うというもの。今回の敵は、1のボスだった魔術師モンデインと、2のボスだった魔女ミナクスが残した子供(?)とも言うべきエクソダス。という事は、1および2の続きという事なのだが、実際にはあまり世界設定が似通っていない。
地上および町の中は、トップビューのごく普通のドラクエ的(というかドラクエがウルティマ的なんだけど)な画面。敵はシンボルとして地上をうろついていて、触るとエンカウントする。画面が変わり、チェスのように1コマずつ動かす戦闘画面になる。
地上で特徴的なのは、「夢幻の心臓」などと同じく、「視界の届かないところは見えない」という仕組み。これは、高い木や山など、主人公の視界をさえぎるような物が画面内にある場合、主人公の位置から見てそこから向こうは見えない(真っ黒で表示される)というシステム。考えると自然なシステムなんだけど、実際にはマップのチップ単位で視界が決定されるので、ちょっと移動するとガタガタと画面が大きく書き換えられ、慣れないと何がなんだかわからない。
地下は3Dダンジョンで、ウィザードリィ風になる。敵とのエンカウントも、歩いているとランダムに発生する。
ま、ゲームとしての基本的な部分は、大体ドラクエ的というか、一般的ではあるんだけど。でもやっぱり自由度が高すぎるんだよね。何していいか分からない。日本流の、「こっちだよ」って手を引っ張ってもらう形のRPGに慣れていると、このウルティマスタイル(というか洋ゲースタイル)はなかなか厳しい。
それでも私は必死にやった。Beepや、あとはなぜか知らないがPCゲームの攻略本がうちに転がっていたので、それを参考にしつつ何とか進めていった。
まず序盤が大変なのはウルティマの伝統だけど、このIIIで困るのは、キャラの能力値が簡単には上がらないこと。単に敵を倒して経験値を積むだけじゃ強くならない。能力値を上げるには、なんとか船を手に入れて、海にある渦から別大陸に行き、そこにある神殿をそれぞれ訪れないといけない。厳しいね。
そこで、序盤はそれを見越して、最初のキャラメイク時に必要な能力を十分割り振っておき、不足がないようにする。戦士系のキャラにはストレングスが必要だし、僧侶系なら法力が必要(PC版で言うインテリジェンスかな)。これが上手く出来ないと、序盤で何も出来なくなってしまう。
このへんは、攻略本があって良かった。それを考えるところからやってたとしたら、途中でめげてたかも知れない。
このゲームは確かに名作であるし、このスペックで作られているわりには、自由度の高さなどほめるべき部分も多々ある。
ただ、実際こうして日本のRPGにやりなれてみると、戦闘などのバランスに問題があるのが分かる。特にドラクエは、従来のRPGよりゲームバランスに気をつけて作られており、また日本ではそれがスタンダードになった。
こうして、ウルティマをやる事により、かえってドラクエの良さ、そして日本とアメリカのゲームの違いというのが分かったのであった。