●
その他
その他の機種をまとめて。
<PC>
●ローグ (アスキー 1986-01)
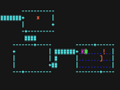
-
元はUNIXの有志が作ったゲーム。こんなのを市販するのかよ、と本気で思ったけど、そこそこ売れたっぽい。パッケージソフトとして欲しかった人が結構いたようだ。少々めんどうだけど凄く良くできたゲームで、類似のゲームが今も世界中で遊ばれている。
●SeeNa (システムソフト 1986-02)
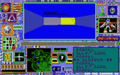
-
あの「たいにゃん」のゲーム。たいにゃんはBeepで連載を持っていたから、なんとなく親近感があったのだ。ゲーム自体は、ポリゴンで出来た街(?)の中を走り回るというちょっとレースっぽいゲームで、結構隠れた名作というか、細々と評価されていたようだ。
●クリスタルプリズン (ボーステック 1986-04)

-
絵がかなり独特なのだが、シナリオも独創的。いきなり主人公が記憶喪失になっていて、何が起こっているのかさっぱりわからない。自分で情報を集めないとなんだかわからないというのは「ZORK」でも使われていたが、それの正当進化版と言えよう。
●クルーズチェイサー ブラスティ (スクウェア 1986-04)
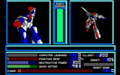
-
物凄く発売が遅れたが、大きな注目を浴びたアニメRPG。日本サンライズの協力で作られたロボットアニメーションが動きまくるというRPG。動きはほんとPC-88とは思えないくらい凄い。が、RPGの戦闘時にいちいちそれをやられてもウザイというのは正論だ。坂口氏はこの頃から「見た目で押して行く」と言い切っており、それが後のFFまでずっと受け継がれていくのだから、ある意味信念だ。
●北斗の拳 (エニックス 1986-05)
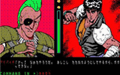
-
当時腐るほどあったアドベンチャーの一つ。原作の北斗の拳の世界観に沿ったストーリーの中をバットとケンシロウが冒険する。特徴は、戦闘場面になると秘孔を突くための方眼が表示される事。キャラによって秘孔の位置は違うので、色々調べないといけない。どこかで奴隷のじいさんが「恋のハートは片思い、私の彼は左利き…」などと歌っていてそれが秘孔の位置のヒントなのだが、なぜそれをじいさんが知ってるのか、なぜそれを歌っているのか、そもそも「私の彼」ってなんだとか、考え出すと悩んでしまう。
●レリクス (ボーステック 1986-06)
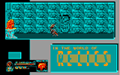
-
ひどく風変わりなアクションRPG。主人公の初期状態は「幽霊」で、以後近くの生物に乗り移りながらゲームを進めていく。SF調の舞台なのだが、そこは何なのか、自分は何者なのか、何をするのかがほとんど示されない。全てが謎のまま進んでいく、不思議な感覚を持ったゲームだ。
●覇邪の封印 (工画堂 1986-07)
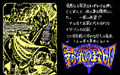
-
RPGが飽和状態になるにつれ、アクション性を取り入れるなど目先を変えた趣向のゲームが増える中、唐突に出てきた本格派RPG。とにかく地道にお金や経験値を稼がないと何も出来ないと言うゲームで、クリアするためには大変な労力が要る。立派なマップが付属品としてついてくるが、初期状態では自分のいる1マスしか見えないという恐ろしいゲームなので、マップは必須だったのだ。
●殺人倶楽部 (リバーヒルソフト 1986-08)

-
いい加減RPGが流行ってきてて、本格アドベンチャーはここいらで末期を迎えていたのだが、リバーヒルソフトやシンキングラビットなどは円熟期と言う事でこの時期に傑作を連発していた。私もこういうタイプの本格派アドベンチャーは好きなのだが、これ以後廃れていったのは寂しい。
●177 (マカダミアソフト 1986-09)
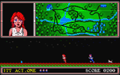
-
国会でも取り上げられたというのが伝説になってるヤバイゲーム。タイトルの「177」は、刑法177条(強姦罪)の意味。タイトルで分かる通り女の子を襲うのだが、なんつーか追いかけて手榴弾を投げて捕まえるという壮絶なゲーム。捕まえた後も凄い。色んな意味で凄い。凄すぎる。
●ザナドゥ シナリオ2 (日本ファルコム 1986-10)
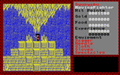
-
大人気作となったザナドゥの続編。ザナドゥ自身が「ドラスレシリーズ」という作品群の一部なので、こんな名前になっている。基本的にゲームシステムは変わらないのだが、マップがやたらと複雑になった。前作はダンジョンを1階、2階と進んでいくのだが、シナリオ2ではどの階がどの階に繋がっているかがバラバラ(イシター方式)。アクション要素もきつい。
●ロマンシア (日本ファルコム 1986-10)

-
ザナドゥと良く似たシステムを使って、もう少し軽い感じのアクションRPGを作りたかったようだ。が、軽いのは見た目だけで、中身は極悪の難易度を誇る。ほとんどヒントも無しに、理不尽かつ面倒な謎解きを強要される。攻略本無しでクリアするのは確実に不可能で、攻略本があったとしてもクリアできるかどうか微妙である。そんなゲーム。私はラスボスまでは行ったよ…。
●大戦略88 (システムソフト 1986-10)
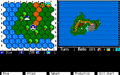
-
PC-98で出た「現代大戦略」の移植。PC-98版は書くの忘れてた。おなじみのHEX制ウォーシミュレーション。単にコマを動かすだけでなく、生産計画まで考えないといけないという本格派。生産のためには都市からの収入を得なければならず、そこまでやると戦術級の枠をはみ出しているが(大戦略だからいいのか)、それはそれで色々考えさせられて面白かった。
●ディーヴァ (T&Eソフト 1986-11)
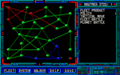
-
7機種(PC-98、PC-88、X1、FM-77AV、MSX1、MSX2、ファミコン)のタイトルをリリースし、それぞれ世界観を共有するが主人公の異なるゲームにしたという壮大な実験作。別機種の間で、パスワードによるキャラクタの移動ができ、単一のシナリオでは出来ないイベントなどを遊ぶ事が出来た。もう少し練りこんでいれば、という感じはする。
●信長の野望 全国版 (光栄 1986-12)

-
初代信長から3年経って発売された待望の新作。名前の通り、日本全国が舞台になっており、スケールが大幅にアップしている。コマンドの内容や戦闘もグレードアップしており、大変やり応えのある作品だった。歴史マニアの人達もかなり満足行くゲームだったのではないだろうか。
●夢幻戦士ヴァリス (日本テレネット 1986-12)
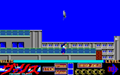
-
女子高生がセーラー服や露出度の高い戦闘服で剣を振って異世界の怪物と戦ったりする、もう80年代オタク文化の象徴のようなゲーム。マップが広いのはいいのだが、障害物も何もなくただ広いだけで、そこをウロウロしないといけない。全体的に苦痛感の強いゲームだった。
●ティル・ナ・ノーグ (システムソフト 1986-12)

-
PC-9801版。シナリオやキャラクタを自動的に生成して、毎回違った設定でゲームが出来ると言うとても珍しいゲーム。と言っても、そこまで本格的なシナリオを生成するわけじゃないけど。いくら9801とは言え、当時のPCの能力でそれをやろうとする根性は評価できる。
<MSX>
●らぷてっく2 (dbSOFT 1986-02)
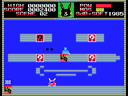
-
ジャンプアクションなのだが、少々パズル要素もあり、かなり難しいゲームになっている。浮遊するような主人公のジャンプ感覚に慣れないとどうにもならない。同じ所で何度も死んでメチャクチャイライラするゲームだが、その分クリアすると爽快。
●グラディウス (コナミ 1986-07-25)

-
ファミコン版に対するアドバンテージとして、「レーザーが長い」というのが挙げられる。スプライトで描いてないので、長い(そしてなぜかちょっと太い)レーザーを出せた。しかしオプションは相変わらず2個。ステージが1つ増えて全8ステージなのも、ちょっとした追加要素か。
●スーパートリトーン (ザインソフト 1986-12)
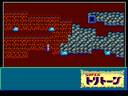
-
あのザインのアクションRPG。トリトーンの続編らしい。ひたすら単調な洗脳系BGMの中、のたのた動く主人公を操って延々スライムなどを倒し続けるゲーム。セーブが無いのでクリアするなら一日やってないといけない。私は律儀にもこの退屈なゲームをクリア目指してひたすらやり続けた。が、半日ほどしてハマった。何をしても先に進まなくなった。これまでのプレイがもったいないので、先に進もうとあらゆる場所であらゆる事を試したが、何も起こらなかった。もうこれ以上出来る事は無い、と確信を得るまでプレイしたあと、そっと電源を切り、2度とプレイしなかった。
●ガルフォース (ソニー 1986-12)

-
ファミコン版とは少々違う内容。単色スプライト中心ながら、キャラクタによる攻撃の違いを上手く表現していて、しかもパワーアップ後の攻撃がかなり派手。確かにファミコン版より絵はショボいが、私はMSX版の方がどちらかと言うと好きだった。
●トランプエイド (東芝EMI 1986-12)
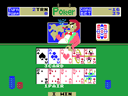
-
うちの伝説ワゴンゲーム三銃士の一角。元はPCのゲーム。賭けトランプ(ポーカー、セブンブリッジ)をやって世界を救うという壮大なゲーム。ま、ただのトランプゲームなんだけど。このゲームには恐ろしいバグがあって、何かの条件を満たすとなんとエラーを出してBASICの画面に戻ってしまうのだ。もちろん、リストも見れる。ROMのゲームなのにBASICに復帰してしまうなんて…という新鮮な驚きがあった。
<セガマークIII>
●阿修羅 (セガ 1986-11-16)

-
戦場の狼や怒にそっくりなゲーム。この手のハードメーカーの常だが、他社の出した面白そうなゲームを、自社ブランドでちょっとアレンジして出すのは基本中の基本だ。しかし似ているのは見た目だけで、なんかこうゲームとしてはかなり終わってる感じだった。一度試しにやってみて欲しい。
●スペースハリアー (セガ 1986-12-21)

-
実に良く頑張ったゲーム。大量のスプライトを拡大縮小させて実現しているアーケード版の処理を、パターン定義で無理矢理切り抜けている。そのためキャラクタの周りに四角い「枠」が残ってしまうが、動きとしてはちゃんとスペハリしている。努力の勝利である。
その他に1986年に発売されたゲームとしては、以下のような物がある。
<PC> トランシルバニア2、はーりぃふぉっくす雪の魔王編、A列車で行こう、リグラス、アルバトロス、マーベラス、ウイングマン2、オペレーショングレネード、ファイナルゾーン、アーコン、ロストパワー、カレイドスコープ発汗惑星、摩訶迦羅、デイドリーム、α、冒険浪漫、リバース、ファンタジー、ウイバーン、カサブランカに愛を、スターシンフォニー、アステカ2太陽の神殿、うっでぃぽこ、トップルジップ、アルゴー、アートオブウォー、めぞん一刻
<MSX> レイドック、アメリカントラック、聖拳アチョー、ナイトロアー、ダムバスター、白と黒の伝説(輪廻転生編)、エミーII、トリトーン、ピピ、ザナック、クロスブレイム、アラモ、スカイギャルド、ツインビー、ナイトシェード、テグザー、地球戦士ライーザ、ガーディック、カモン!ピコ、夢大陸アドベンチャー、キャッスルエクセレント
なんかもうとりあえず大量にゲームが出た年だった。というより、年々増え続けているといった方が正しいのだが。
特にファミコンソフトの増えっぷりは尋常ではなく、隆盛を極めた。しかし、86年にはアーケードゲーム基板の能力が質的に大幅に変化して、ファミコンとの差は非常に大きくなった。当然、「もっと高性能なマシンが欲しい」というユーザの要求に結びつく。セガマークIIIはそれに応えたとは言いがたいが、やがてそれがPCエンジンやメガドライブなどの次世代機への呼び水となる。