| メーカー | エニックス | 発売日 | 1987-01-26 |
| 機種 | ファミコン | ジャンル | RPG |
| 評価 | ★★★★☆ |
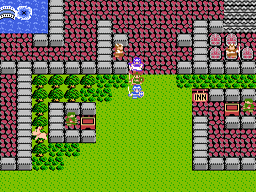
| ファミコンRPGの火付け役となったドラゴンクエストの続編。爆発的なヒットとなり、「ドラクエ」の名前は一大ブランドになった。 |
●
個人的最熱中ドラクエ
言わずと知れたドラゴンクエストの続編。開発は順調に遅れ、86年内発売予定が、87年にまでズレこんだ。当然ながら発売日から飛ぶように売れ、一つの社会現象にまでなった。
当然、私の周りでもやってる人は多かった。同じ部活の友達の家に遊びに行った時も、ずーっとこのゲームばっかりやっていた記憶がある。この頃は他にもたくさんゲームが出ていたが、このゲームの人気はぶっちぎりだった。それくらいみんな遊んでいたのである。
前作からは全ての面にわたってパワーアップしている。1人だった主人公が3人のパーティを組めるようになり、当然ながら武器や魔法なども大幅に増えた。冒険の舞台も広がり、街の数も増え、モンスターも大量にいる。インターフェイスもかなり改善され、いちいち「かいだん」「とびら」などとやらなくても良くなったし、人と話し掛ける時もそちらを向いていればいいという事になった。とにかく、あらゆる面で改善されている。
シナリオもかなり本格的になっている。前作は、主人公は誰とも知れない浮浪者の一人で、王様に端金をもらって竜王を倒しに行くと言う感じだったが、IIではもっと本格的な導入部がある。ムーンブルクがハーゴンの軍勢に襲われ、その生き残りが主人公のいるローレシアの城にやってくる所から物語は始まる。絵がいつものあれなので感情移入しづらいが、良く良く考えるとRPGの中でもかなりシリアスな導入部を備えた作りになっている。
主人公はローレシアの王子であり、前作の主人公の子孫という事になっている。前作の主人公は「ロトの血を引く者」と言われているので、このIIの主人公達もまたロトの末裔である。勇者は、竜王を倒したあとローラ姫と結婚し、そのままアレフガルドから旅立っていったらしい。昨今はRPGの「I」「II」などは単なるシリアルナンバーに過ぎず、物語上の繋がりなんか全くなくて、「同じタイトルだからみんな買ってね」くらいの意味しか無い。それを考えると、このように前作と物語上の結びつきが強いこの設定は好感が持てる。
主人公であるローレシアの王子を操作し、世界征服を企む悪の神官ハーゴンを倒すために、親戚であるサマルトリアの王子、ムーンブルクの王女を仲間にして、冒険を繰り広げるというのが全体のストーリーである。
前作では、パスワードの長さの制限のせいか、明確なフラグというものが無かった。シナリオの進み具合は、どのアイテムを持ってるかで示される。従って、シナリオ自体をあまり複雑に出来ず、要するにアイテムを順番に手に入れていくだけというものであった。
それに比べるとこのIIではかなり凝った作りになっている。まず、最初の目的である2人の仲間がなかなか味方にならない。サマルトリアの王子は放浪癖があり、なかなかつかまらない。ムーンブルクの王女も、素直に仲間にはなってくれない。
紆余曲折あって3人パーティになると、そこから本格的冒険の始まりという感じになる。ローレシアの王子は呪文の全く使えない戦士タイプだが、ムーンブルクの王女は回復呪文も攻撃呪文も使える賢者タイプ。サマルトリアはその中間で、そこそこ戦えるし、呪文も使えるという感じだ。
呪文の数は、例えば後のドラクエIII以降に比べるとだいぶ少ないんだけど、その分一つ一つの呪文に特徴があり、「それを覚えるとすごく楽になる」という節目の呪文がいくつかあり、ゲーム全体にメリハリがあった。例えば「バギ」「ベホマ」「ザラキ」などという呪文を覚えると、「よっしゃー」という気持ちになる。このへんは以後のドラクエよりずっと良い。
アイテムについても同様で、「いかづちのつえ」や「いなずまのけん」なんかを手に入れると、かなり楽になるので、嬉しくなる。RPGはともすれば単調な作業の繰り返しになりがちなので、こういうメリハリは良い。
シナリオの展開的も上手く工夫されていて、飽きさせない作りになっている。途中までのシナリオは一本道なのだが、船を手に入れたあたりから急に幅が広がり、行く事の出来る場所が多くなる。その中で5つの紋章を手に入れる事が目標となり、好きな順番で取って構わない。紋章を手に入れる方法は5つそれぞれ異なっており、「こんなところにあったのか!」と思わせるものもある。
また街のあちこちに、鍵を必要とする扉が見つかるが、その鍵自体はかなり進めないと手に入らない。手に入れると、今まで行けなかったあんなところやこんなところに行けてしまうわけで、かなりワクワクする。このへんは本当に良く出来ている。
それから、「旅の扉」と呼ばれるいわゆるワープゾーンが世界のあちこちにある。意外な場所から意外な場所に飛ぶ事が出来て、このへんは「ウルティマ」などの古き良きRPGを思わせる。
その他にも、非常に強力だが身につけるとマイナス効果も出る呪いのアイテムや、買い物時にランダムにくれる「ふくびきけん」、かなりの経験値を得られる「はぐれメタル」、使うと何が起こるかわからない「パルプンテ」など、本当に良くこれだけ前作からパワーアップさせたなと思うくらい、様々な要素が盛り込まれ、後のドラクエに引き継がれていった。
と色々書いたが、とにかくゲームとして素晴らしく良くできており、みんなが夢中になるのも当然だった。
最初に書いた、私の部活の友達なども、本当に夢中でやりこんでいた。そいつの家は同じ部活の連中が何人もたむろしているような家だったんだけど、とにかくその時はみんなでドラクエIIをやりこんでいたね。
もうパスワード入力からしてゲームだった。ドラクエIIは、前作よりボリュームアップした分、パスワードの方もひたすら長くなっていた。ところがその友達は、兄弟と「BGMが1ループ終るまでに入力できるか」競争をしていて、これをやると結構短く感じる。パスワード入力時のBGMは、元はなんかの歌らしく、1分半くらいある長い曲だ。それが終わるまでに入力し終われば勝ち、出来なければ負けという競争である。これがかなり絶妙な長さで、大体上手く入力しても曲の最後のパートあたりになる。あんまり間違えると、曲が2ループ目に突入してしまう。私も自分でやる時はこれを目安にしており、やたら長いパスワードを入力するわずらわしさが結構軽減する。
私がたまたま遊びに行った時は、その友達はちょうどロンダルキアに辿り着いたばかりで、経験値稼ぎをしていた。またこれが楽な稼ぎがあって、ロンダルキア南部に出てくる「サイクロプス」に対してザラキをかけると良く効くので、サクサク稼げるのだ。このように、特定の呪文が効きやすいなどの属性が敵に設定してあるので、楽に稼げる相手、稼げない相手など色々いる。稼ぎ場所を自分で見つけられるかというのもこのゲームの醍醐味の一つだ。
その後私もこのゲームを借り、やりこんだ。ほんと、夜中までやってたね。面白くて。
私が借りてからしばらくして、学校の修学旅行があった。当然その間ドラクエは出来なかったんだけど、もう続きがやりたくてやりたくて仕方なかったね。ほんと。
今考えても、ほとんどの場面に色んな思い出があるよ。リリザの町でやたら薬草と毒消し草を買って福引券ためたっけ、とか。ムーンブルクの王女を助けてからは、バギでムカデを殺しまくったっけとか。海に出たらメドゥーサボールやしびれくらげをいかづちのつえで叩きまくったっけとか。
このゲームには色々攻略の役に立つ裏技や、こうすれば楽になるという方法がたくさんあり、同級生達と色々情報交換したものだった。例えばさっきの福引券による金稼ぎもそうだし、他にも裏技レベルのものとしては、「いかづちのつえ」を何度も手に入れて売り払う方法(いかづちのつえは高く売れるので、これをやるとメチャ楽になる)や、「みずのはごろも」(普通だと1枚しか手に入らない)を2枚手に入れる方法だとか、色々ある。そういうのを知ってるのと知らないのとでは、クリアにかかる時間や労力が結構変わってくる。
裏技の中でも究極的なのは、「はかいのつるぎ」の重ね持ちである。「はかいのつるぎ」というのは、このゲームでの最高の攻撃力を誇る武器なのだが、呪われているので普通装備しない。しかし、ある裏技を使うと、別の武器を持ちながらも攻撃力だけは「はかいのつるぎ」のままという状態になる。当然呪われていない。そこで、その「別の武器」を「はやぶさのけん」(弱いが、1ターンに2回攻撃できる)にすると、なんと「はかいのつるぎ」の攻撃力で2度攻撃できるようになる。これを使うとかなり強力で、普通はなかなか倒せない「アークデーモン」などの敵もわりと簡単に倒せるようになる。有名な裏技だけど、これ知ってると終盤すごく楽になるんだよね。
また、ゲームバランスがまた絶妙にいい。今やると多分少し難しく感じるかも知れないけど、それでもかなり良好なバランスである。イベントとイベントの長さが適切で、ちょっと単調になってきたなと思ったあたりで次のイベントに突入するようになる。先ほども書いた通り、呪文の習得や敵の強さなどにもメリハリがあるので、ある程度冒険のパターンが固まったあたりで新しい要素が入ってくるようになる。堀井雄二はとにかくバランス調整に命をかける人らしく、さすがとしか言いようがない。
だから中毒者が発生するんだね。ほんと、ちょうどいったんやめようと思ったあたりで新しくやりたい事が発生するように仕組まれていて、なかなかやめるにやめられない。私も実際そうだったし、周囲のみんなもそんな風に言っていた。
そう言うわけで、私自身はブームから少し遅れてプレイしたんだけど、流行ってた時期は凄かったね。毎日のように情報交換があって。どこが一番お金が入るとか、経験値が稼げるとかが話題になったりして。この敵がこんなアイテム持ってるとか、こんなところにこんな物が落ちてるとか、色々あった。
中でも、「ラゴスはどこだ」というのが何度も話題になったね。雑誌にも何度も載ってたし。ラゴスというのは「すいもんのカギ」という重要なアイテムを盗んだんだので、そいつを見つけないとゲームが進まないんだけど、これがまた普通じゃ見つからないような意地悪な位置にいるので、見つけられないという人が多発したのだ。
私はそういうのからちょっと遅れてプレイしたので、大体の謎は前もってわかってしまっていた。もし知らずにプレイしてたらどうだろう。かなり詰まったんじゃないかと思う。それはそれで面白いと思うけど。
で、修学旅行から帰ってきてクリアしたんだけど、楽しかったねー。ほんと。ここまで熱中したRPGは少ないよ。
正直私は、プレイするまでは「ファミコンのRPG」という意味で、なめていた。私は前に書いた通りドラクエIもプレイしていて、確かに面白いと思っていたけど、でも「所詮ファミコンのRPG」という印象は拭えなかった。私の中ではRPGとはウィザードリィやウルティマであり、せいぜいブラックオニキスやファイヤークリスタルなのだ。ドラクエはどうもちょっと…お子様向けって感じかな、という感じだった。
けど、ドラクエIIをやってそんな考えは吹っ飛んだね。このゲームは凄い、と。確かに、RPGの2大巨頭であるウィザードリィ、ウルティマには、本格度という意味では全然届いていない。しかし少なくとも国産RPGという観点で見れば、システムが単純になってはいるがほぼ最高峰ではないかな、と思うようになった。それほどに素晴らしいゲームバランスを持っているというのが私の感想だった。
そんなわけで、このゲームも滅多に出ない4つ星となっている。
さて、その3年後。もうすでにスーファミが発売されようかという時期になっていたし、ドラクエもIVまで発売されていたのだが、私はそこでファミコンを購入した。なんと、それまでファミコンを所有していなかったのだ(じゃあどうやってゲームしてたの、と思うかも知れないが、なんか色々手段はあったのだ)。けど、やっぱりドラクエなんかは最初からやり直してみたいなーと思い、中古のファミコンを安く買ってきた。そして、ドラクエをIから順番に買い揃えていった。
で、まずドラクエIをクリアし、次にドラクエIIに挑戦した。「やっぱり面白いなー」と思いつつ順調に冒険を進め、ハーゴンの城の近くまで攻略した。
で、これは誰がやってもそうだと思うんだけど、ロンダルキアに辿り着いた時のレベルと、最後ハーゴンの城を攻略するのに必要なレベルに結構差があるので、ロンダルキア台地で結構レベル上げをしないときつくなる。
なので私も頑張ってレベル上げをしていたんだけど、そのうちふと思った。ここで頑張ってクリアするのもいいけど、どうせエンディングは一度見た事があるわけだし、そこまでの感動は無いかも知れない。だったらここで一生懸命経験値上げても仕方ないんじゃないかな、と。
その時、私の中で一つの考えが浮かんできた。「パスワードを解析したらどうかな」、と。どうせ普通にレベル上げて普通にクリアしても、昔と結果が変わるわけじゃない。だったら一つパスワード解析に手をつけて、最強キャラをいきなり作ってやろうかと。
ドラクエIIのパスワードはかなり長く、しかも可変長(仲間の人数やアイテムの数によって、パスの長さ自体が変わる)なので、一目見た時から解析は困難だな、と思っていた。しかしシャーロック・ホームズも、人の手で作られた暗号に解けないものは無いと言っていたじゃないかと思い、解析に手をつけた。なんか当時の自分は無駄に自信があり、絶対解けると思い込んでいた。
そして、私の挑戦は始まった。
まず、ごく普通にレベル1、経験値0、所持金なし、アイテムなしなどの最低の状態を作り出し、名前を変えながらいくつもパスワードを収集した。そして、解析に必要な最初のとっかかりを発見した。
全く同じ状態から、見た目の違うパスワードが8個取れる事に気づく。これは、変種を生み出すための情報が少なくとも3ビットは付加されている事を示している。
そして、所持金や経験値ゼロなどの最低状態で、特定の名前のパスワードでは、その中に「あいうえおかきくけ」のように見た目で連続する文字が現れる事がある。ここが最大のヒントである。このように並びが現れるパスワードを多数取り、内部的な文字表の並びを解析できた。
で、並びの文字列がある部分は、内部的には「0、0、0、0…」のような「なんのビットもない」情報を表していると考える事ができる。最低状態だからね。更に良く調べると、上記のように「あいうえおかきくけ」の代わりに、「あうおきけさすそ」のように、1個飛ばしで文字が並んでる場合もあったし、2個飛ばしの場合もあった。
以上の結果から、各文字の情報は「前の文字との差分」で表されていると考えられるし、また変種ごとにそれらの差分に+1ずつ、+2ずつ、+3ずつなどという「ずらし」が入ってると考えられる。だから、「あいうえおかきくけ」のようなシーケンスのパスワードが発見されるのだ。
このように、最終的に文字化する際の方法の推測が済んでしまえば、後は楽になる。具体的に、金や経験値を1ずつ増やしたり、名前をちょっとずつ変えたりしながらパスワードを取れば、どの部分のビットがそれらの情報に当たるのかがわかるようになる。
その結果、かなり巧妙にバラされていたが(経験値を表す数値の5〜8ビット目はここ、9〜12ビット目はここ、などというようにビットごとにシャッフルされている)、最終的にはそれぞれの情報がおさまっているビットを特定できた。
これにより、与えられたパスワードを解析してその中身を調べる事は可能になったのだが、まだ自分で生成する事は出来なかった。というのも、チェックサムとして機能しているいくつかのビットの法則がつかめていなかったからだ。そのビットは、明らかにチェック用として働いており、実際に情報を表しているビットの合計だかなんだかに基づいて計算されている。そこが合わないと、「じゅもんがちがいます」と言われるように出来ているはずだ。
問題は、どういう計算式を用いているか。そして、どの時点で計算を行っているかという事だな。計算式にMODなどが使われているとちょっと解析がややこしくなる。また、例えば差分を出してからチェックサムを出しているのか、その前なのかというタイミングも重要である。
…と言う事で、この難関を乗り切れば最強パスワードを作れたのだが、実際にはそこまでで時間切れというか、飽きたというか、とにかく別の事をやり始めてしまったので、最終的には解析しきれなかった。無念。
今やれば、最後まで解析する自信はあるが、結局今となっては「だからなんなの」というレベルになってしまっているので、恐らくやらないだろう。当時から自己満足に過ぎなかったわけだし。
話がだいぶそれたな。
とにかく色んな意味で楽しめた作品だった。私の所有ゲームデータベースの中でもかなりの高得点を誇っている。名作中の名作である。